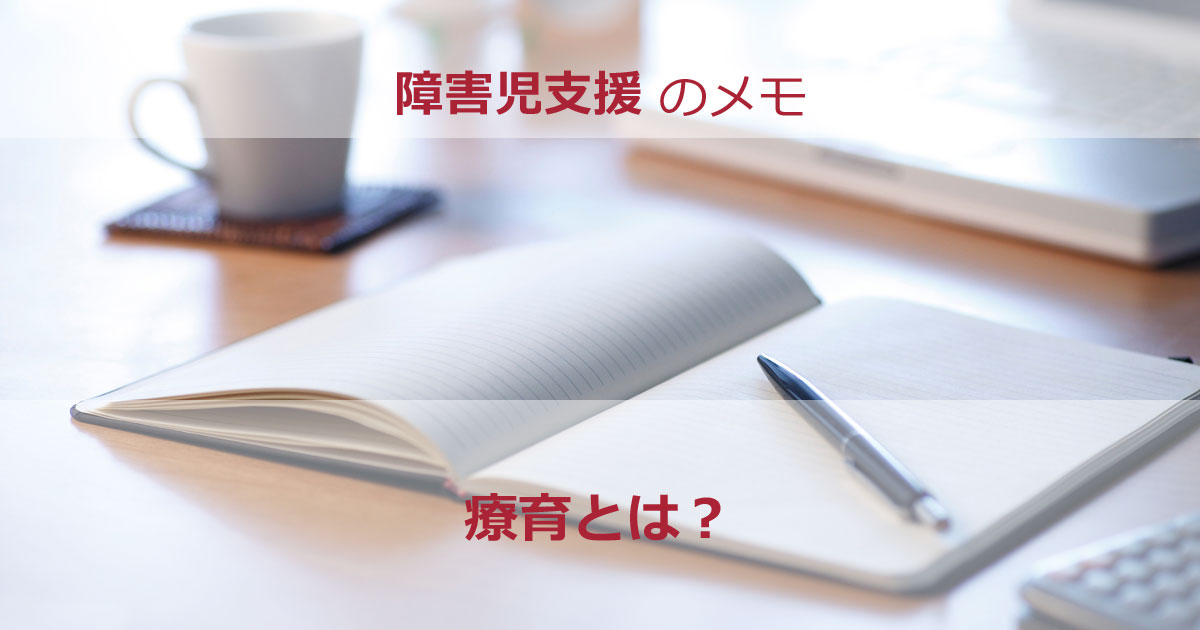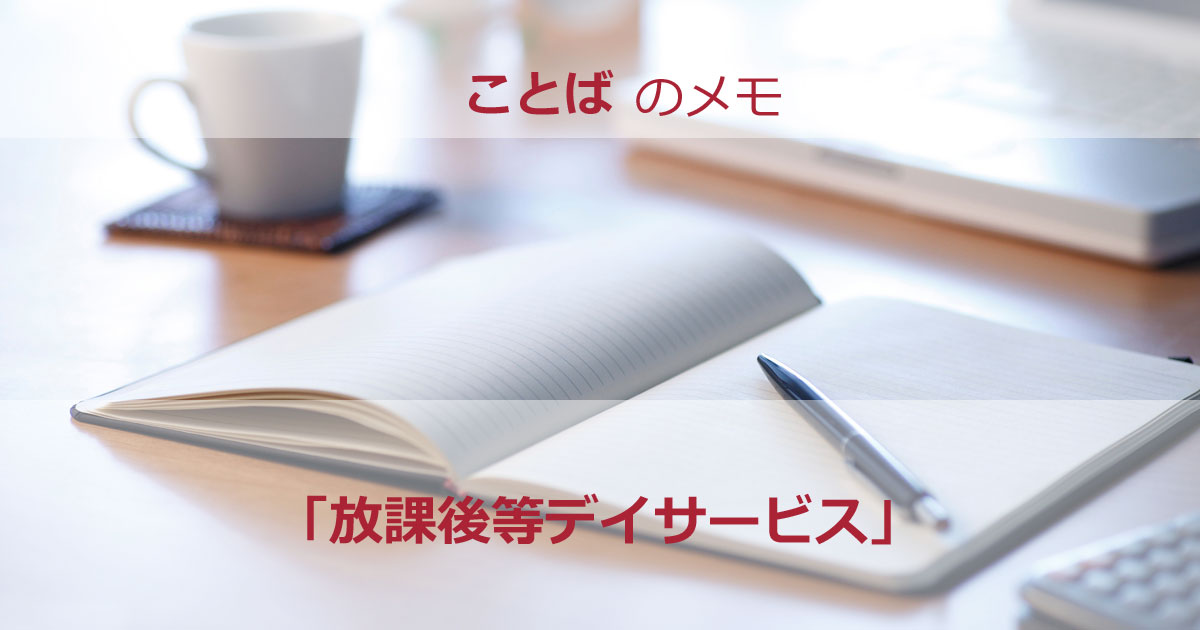お子さまの発達が気になって、療育を受けさせるべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか?
「療育って何?」
「自分の子どもに療育は必要?」
「本当に療育は必要?」
このような疑問をお持ちのご家族の方に、「療育」について分かりやすく解説します。
療育とは?
療育は「発達支援」ともいわれ、身体障害や発達障害・知的障害などの障害のあるお子さまや可能性のあるお子さまに対して、将来の自立した生活と社会への参加が出来るように、一人ひとりの発達状況や障害の特性に応じた支援・援助を行うことです。
療育は「治療」と「教育」
療育は、障害のあるお子さまに「治療」と「教育」の2つの観点でアプローチすることです。
療育における「治療」とは?
お子さまの「障害が原因による問題行動を治療していく」ことです。
たとえば、ADHD(注意欠如・多動症)のお子さまが、学校などで友達に「バカ」と悪口を言って問題を起こしていたとします。
治療の対象となるのが、悪口を言うという行動です。
療育を行うことで、問題となる行動が出ないようにしていきます。
療育における「教育」とは?
お子さまの「問題となる行動を止めるにはどうしたらいいのか」を、お子さまだけでなく、ご家族にも教えて伝えていくことです。
たとえば、悪口を言ってしまうお子さまやご家族に
- 悪口を言いたくなったらどうすればいいのか
- どうすれば悪口を言わなくなるのか
- ご家族はどのように対応すればいいのか
などについて教えて伝えていきます。
療育ではどんなことをする?
療育は、問題行動をするお子さまに合わせて様々なアプローチを行います。
たとえば、「悪口を言ってしまう」お子さまの場合、以下のアプローチをしていきます。
- StEP1お子さまの問題行動の原因を考える
- どのような家庭環境なのか?
- 学校での環境は?
もしかしたら、お子さま自身が虐待を受けていたり、同じ言葉を言われていて、その言葉を言っているのかもしれません。もちろん、それ以外の理由もあるかもしれないので、会話や行動から汲み取っていきます。
- StEP2お子さま自身について考える
- 体や心は、同年代と同じように発達しているか?
- 性格は?
- どんな時に、誰に、問題行動が出てしまうのか?
色々な情報をもとに、「悪口を言ってしまう理由」を考え、「悪口を言わなくてもいい方法や対策」を試していきます。
悪口を言ってしまうことに対して- 悪口を言いたくなったらその場から離れる
- 悪口を言いたくなる人に近づかない
などの考え方を伝えたうえで- 悪口を言われたらどんな気持ちになるのか
- 悪口を言わないためにはどんな方法があるのか
お子さま本人が考える機会を作ります。
- STEP3悪口を言わなかったら褒める
悪口を言わなかったら褒めることで、お子さまが「悪口を言わなくても過ごせた」と思える時間を増やしていきます。
このようなアプローチを、数週間から数か月続けて結果が出れば継続し、上手くいかなければ再度アプローチ方法を検討していきます。
「問題となる行動」は、お子さまによって違います。
同じような問題行動を起こすお子さまでも、育った生活環境や性格などが違うため、基本的に同じアプローチではなくお子さまに合ったアプローチを行います。
療育の必要性
療育は、お子さまの発達状況や特性に合わせて、個別の支援計画を作成してその計画に沿って支援を行います。
「出来ること」や「出来ないこと」の原因を見極め、その原因に応じた支援を行うことが必要です。
お子さまの成長スピードは一人ひとり違います。特に障害のあるお子さまはその差が大きいため、お子さまの状況や発達特性に合わせた支援をすることが必要です。
療育の目的
療育の目的は、「障害のあるお子さまの自立を目指す」ことです。
将来的に日常生活や社会生活を円滑に過ごせる自立した生活を送れるように、お子さまの障害の程度や特性に合わせて様々な方法で支援します。
社会性スキルの向上
社会的スキルの向上は、療育における重要な目的の一つです。
他者と適切なコミュニケーションをとり、感情を理解し表現する能力は、社会生活において特に大切です。
療育では、他社とのコミュニケーションを円滑に築くための支援が行われます。
日常生活スキルの向上
お子さまが日常生活で自立するためには、食事・排泄・着替えなどの基本的な行動が、自分で出来るようになることが大切です。
療育では、日常生活の基本的な行動を習得するための支援が行われます。
学習能力の向上
学習能力の向上は、学校生活での適応能力を高めるために必要です。
お子さまの学習障がいや注意欠如・多動性障がい(ADHD)に対する支援が行われ、読み書きなどの基本的な学習能力の向上を目指します。
自己肯定感の向上
自己肯定感の向上も、療育の重要な目的です。
お子さまの得意な事や能力のあることを伸ばし、苦手なことは出来るだけ配慮する支援を行うことで、自己肯定感が高まり新しいことに挑戦する意欲や自分への信頼感が育まれます。
ご家族の支援
療育は、お子さまの自立支援と同時に、ご家族の支援も重視しています。
「困りごとや悩みごとを誰かに話せる」という安心感を得ることもできます。
お子さまが放課後等デイサービスなどに通っている間に、ご家族の時間を確保することもできます。
自立を目指すために、できることを増やし、自己肯定感を高めていくことが療育の役割です。
「発達支援」とは、「療育」の概念を拡大させたもので、障害のあるお子さま本人だけではなく、ご家族への支援、保育園や地域連携などを含めた包括的な支援を指します。現在では、「療育」も同様に発達を支援する働きかけをひとまとめにした言葉として使われることが多いため、ほぼ同じ言葉として扱われています。
療育(発達支援)施設とは?
「療育施設」というのは療育を提供する場の総称で、「療育センター」や「児童発達支援センター」「放課後等デイサービス」などがあります。
療育施設の中には公的な施設も民間の施設もあり、提供するサービスや療育のプログラムは療育施設ごとに違います。
療育と保育の違いは?
「療育」と「保育」は、お子さまが社会生活・集団生活を送るための支援をおこなう点では共通していますが、定義上の違いがいくつかあります。
療育とは?
対象:障害のある、もしくは発達に課題のある子ども
目的:特定の子どもの発達を促し、自立した社会生活と社会参加を目指す
活動方針:発達段階やニーズに応じて個々に合わせることに重きを置く
保育とは?
対象:保育を必要とする全ての子ども
目的:就学前までの子どもの日常生活のケアや教育、社会性を育む
活動方針:みんなで参加する活動や集団行動に重きを置く
まとめ
- 療育は「発達支援」ともいわれ、身体障害や発達障害・知的障害などの障害のあるお子さまや可能性のあるお子さまに対して、「治療」と「教育」の2つの観点でアプローチすることです。
将来の自立した生活と社会への参加が出来るように、一人ひとりの発達状況や障害の特性に応じた支援を行うことです。
- 療育は「治療」と「教育」
治療は「障害が原因による問題行動を治療していく」ことです。
教育は「問題となる行動を止めるにはどうしたらいいのか」を、お子さまだけでなく、ご家族にも教えて伝えていくことです。
- 療育の必要性と目的
「出来ること」や「出来ないこと」の原因を見極め、その原因に応じた支援を行い、障害のあるお子さまの自立を目指すことです。
「メモな備忘録」は、私が役に立った事を忘れないように「メモ」しています。
この記事が、お役に立てれば幸せです。お読みいただき有り難うございます。