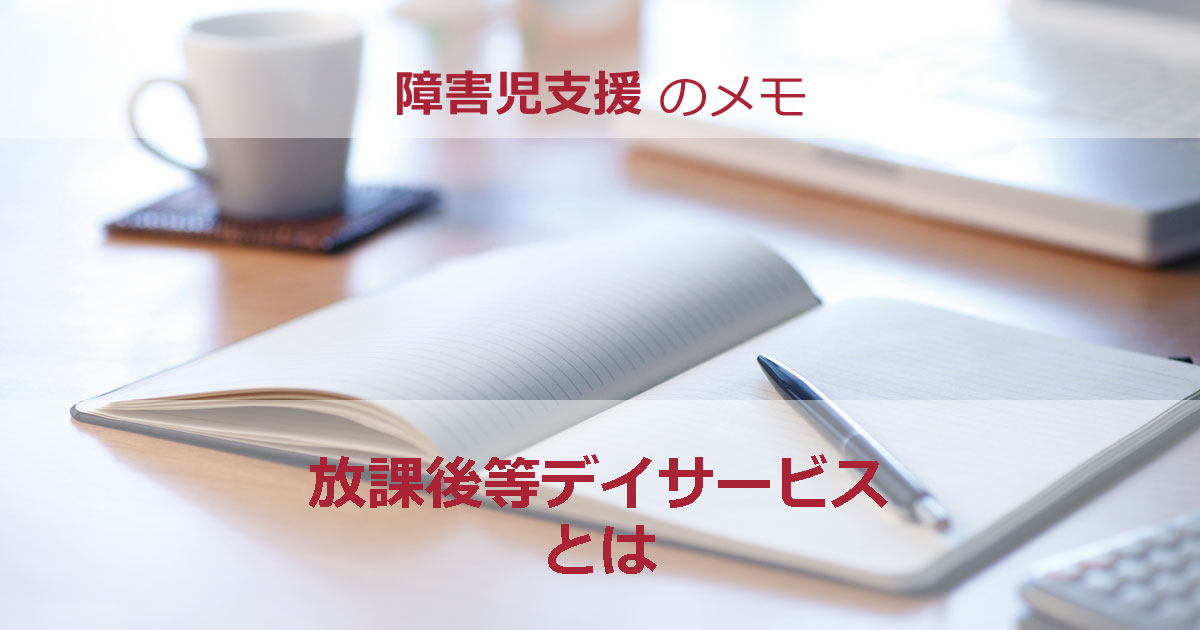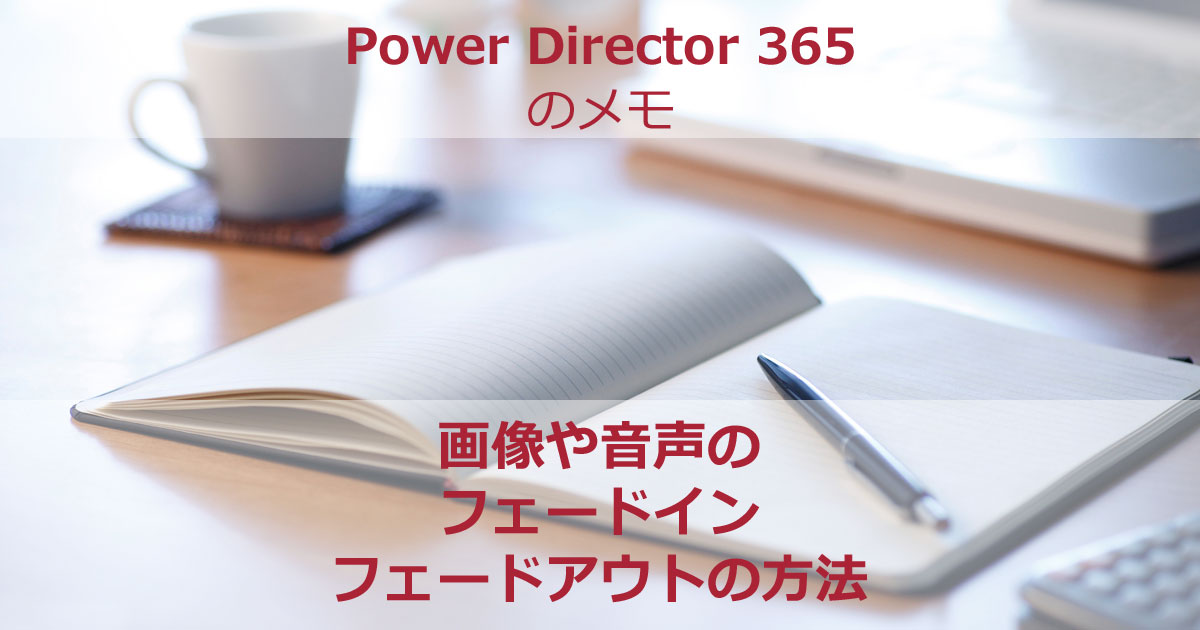放課後等デイサービスは、学校に就学している障害や発達に課題を抱えている子どもを対象とした通所型の福祉サービスです。
この記事では、放課後等デイサービスについて分かりやすく解説します。障害をもつ子どもへの理解を少しでも深めてもらえれば幸いです。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、障害を持っていたり発達が気になる小学校・中学校・高校に通う子どもが、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇中に、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、将来の自立した生活と社会参加を目指すための支援(療育)を行う通所型のサービスです。
一人ひとりに合わせた支援計画を立て、日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けたサポートをおこないます。
主な目的は、障害のある子どもが、自身で出来る事を増やしたり、学校や家庭以外の場所での経験を積み、健やかな成長を促しながら、将来的な社会的自立を目指していく場所です。
放課後等デイサービスを利用できるのは?
利用できるのは小学校1年生から高校3年生まで
放課後等デイサービスを利用できる対象年齢は、小学校・中学校・高等学校に通っている子どもです、
発達の特性について医師からの診断書があり、療育手帳・障がい手帳などを所持していることが原則として決められています。
だだし、医師から療育の必要性が認められた場合には、障がい者手帳は必要なく自治体の判断により利用できます。
保育園・幼稚園・高校以外の各種学校・大学に通っている子どもは対象になりません。
しかし例外として、放課後等デイサービスの支援が終了した際に「福祉を損なう恐れがある」と認められた場合には、20歳まで利用することが可能になります。
障がい者手帳がなくても利用できる
放課後等デイサービスに通っている子どもの中には、療育手帳や障がい者手帳を取得しておらず、きちんとした診断名がない子どもも多くいます。
最近では、知的を伴わない発達障害の傾向のある子ども、いわゆるグレーと言われる子どもで、普通学級に通学しながら放課後等デイサービスで支援を受けています。
ただし、利用には障害児通所支援の受給者証の取得が必要になるので注意しましょう。
年齢による特例
小学校・中学校・高校に就学していることが条件となっていますが、例えば19歳であっても、高校で留年をしたなど場合には特例で利用することができます。
さらに、高校を卒業しても、引き続き放課後等デイサービスを受ける必要性が認められた場合には、満19歳(20歳になるまで)まで利用可能です。
利用料金は?
放課後等デイサービスの利用料金は、利用料金の1割が自己負担。9割は自治体負担となり、1日の利用あたり1,000円程度となります。
また、世帯の所得に応じて、月額0円・4,600円・37,200円の負担上限があり、1か月に利用した日数にかかわらずそれ以上の費用は発生しません。
ただし、施設によっては、おやつやお弁当代など、別途費用がかかる場合があります。
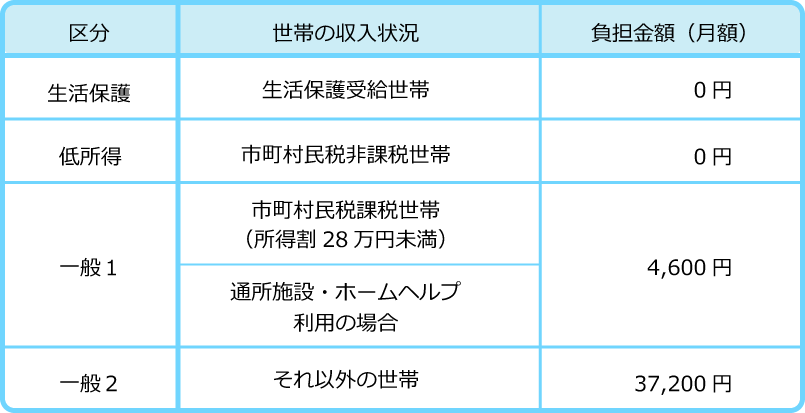
利用頻度は?
利用頻度は、お子さまの状況やご家庭の都合などによって調整できます。
受給者証の申請時に、お子さまに必要なサービス量に応じて月1日から23日(原則)までの上限日数が決められます。
放課後等デイサービスの3つの役割
放課後等デイサービスの役割は、障害のある子どもと、その保護者のサポートが大きな役割です。
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」では、放課後等デイサービスについて3つの役割を定義しています。
子どもの最善の利益の保障
生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流を促進する役割です。
支援を必要とする障害のある子どもに、「生活能力の向上のために必要な訓練」や「社会との交流の促進」を提供し、「学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験」などを通じて、一人ひとりの子どもの状況に応じた発達支援を行います。
共生社会の実現に向けた後方支援
地域社会への参加や、他の子どもも含めた集団の中での成長をサポートする役割です。
放課後等デイサービスは、共生社会実現のために、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策と連携を取りながら、放課後等デイサービスの専門的な知識・経験でバックアップする「後方支援」も役割の一つです。
保護者支援
放課後等デイサービスを利用している子どもだけでなく、その保護者の方をサポートするのも重要な役割です。
子どもの育児に関する相談ができるだけではなく、保護者の方がゆとりを持てるようになるための支援もおこないます。
保護者の方のサポートを通じて、お子さまの発達により良い影響を及ぼすことを目指します。
放課後等デイサービスの支援内容
放課後等デイサービスには、ガイドラインで定められた4つの「支援活動」があります。
- 自立支援と日常生活の充実のたの活動
- 創作活動
- 地域交流の機会の提供
- 余暇の提供
自立支援と日常生活の充実のための活動
子どもが将来の自立を目指すために必要となるスキルを身につけるための支援をおこないます。
例えば、挨拶や、手洗い・片付け・整理整頓、買い物・金銭管理・外出時の行動マナー、基本的なコミュニケ-ションなどがあります。
「できた!」という成功体験を積み重ねていけるよう、一人ひとりの発達に応じた支援を行います。
創作活動
子どもが楽しめる様々な遊び(活動)で、気持ちや感情を表現する事や、豊かな感性を育むための支援をおこないます。
例えば、机上での工作や集団で制作したり、学校の学習とは違う活動を行います。
創作活動には子どもの心を豊かにし、気持ちを開放するということを目指すことを目的としています。
地域交流の機会の提供
特性を持った子どもは、社会へ出ることの困難さを抱えていることも少なくありません。
子どもの社会経験の幅を広げるために、地域の中で多くの人と交流できるような支援を行います。
例えば、公園への散歩やお店への買い物、地域の行事に参加するなど様々な地域活動を通して、経験を積んでいくことを目的としています。
余暇の提供
学校の長期休みや休日に、学校や家庭では経験できない余暇活動の機会をつくり、様々な経験を積み重ねる支援を行います。
例えば、公園にお出かけして昼食を食べたり、自治体の運動施設で自由に遊んだりします。
子どもが自分自身をリラックスする方法を学ぶことや、自分で遊びや活動を選択できるようになることを目的としています。
放課後等デイサービスのプログラム例
施設により提供するプログラムは異なります。また、同じ施設に通っている子ども全員が同一のプログラムを受けるということではありません。それぞれの特性や発達にあわせたプログラムが作られます。
放課後等デイサービスのプログラム例
- 運動プログラム
- 音楽プログラム
- 創作活動プログラム
- パソコンなどを用いるプログラム
- ソーシャルスキルプログラム
- 学習支援プログラム
資格保有のスタッフが療育を行っている施設や、自由に遊べる時間が多くあるなど特徴や形態も異なります。目的に合わせて適した施設を選ぶことが重要です。
放課後等デイサービスを利用するまでの流れ
放課後等デイサービスを利用する場合、施設を見つけてもすぐに利用できるわけではありません。正しい手順を進めていくことで、放課後等デイサービスを利用する事が出来るようになります。
放課後等デイサービスが利用できるまでの手順を分かりやすく解説します。
①自治体などの窓口に相談する
まずは、お住いの自治体に相談しましょう。いつ頃利用したいのか、求める支援・サービスについて事前に相談しておくと、話をスムーズに進められます。
自治体の窓口に相談することで、地域の放課後等デイサービスの情報を教えてもらえることもあるので、まずは自治体の窓口に相談してみてください。
②施設の見学と体験
自治体へ相談して見学をしてみたい施設を見つけたら、見学や体験を申し込みます。
施設に連絡して、施設の見学や通わせたい子どもの特性などを相談しましょう。
ここでは、具体的にどのような支援内容となるのかを相談することが可能です。求めている支援が受けられるのか・どのような方針で支援を提供するのかなどを詳しく聞いておきましょう。
③障がい児支援利用計画案を作成する
利用したい施設が決まったら、申請に必要となる支援利用計画案の作成を行います。作成する方法は2種類あるため、適した方を選択してください。
- 保護者が主体となり施設がサポートして作成する
- 施設に聞き取り調査を行ってもらい作成する
どちらの方法でも問題はありませんが、放課後等デイサービスの利用が初めてで分からないことが多い方や、保護者主体の作成に不安を感じる方は、施設に聞き取り調査をしてもらう作成方法がおすすめです。
④申請書などを提出する
障がい児支援利用計画案の作成が完了したら、利用に必要な書類をまとめて申請書を提出します。保護者の所得を証明する書類や療育手帳などを事前に準備して一緒に提出するようにしましょう。
手帳がない場合は、医療機関や児童相談所等の意見書などの提出を求められることもあります。また、必要書類は自治体により異なるため、前もって何を準備すればいいのかを確認しておきましょう。
⑤調査・審査
申請書を提出したら、それらの書類をもとに調査・審査が行われます。
放課後等デイサービスの利用対象となるための条件は満たされているのか、利用する子どもにとって必要なサービス量などについても検討されます。
⑥受給者証が交付される
放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると受給者証の交付が行われます。
この受給者証を保有していれば放課後等デイサービスの利用料金は1割負担のみです。
調査・審査から受給者証の交付まで、1ヶ月から2か月ほどかかることもあります。
⑦施設と契約をして利用開始
受給者証を受け取れたら、作成した障がい児支援利用計画を持って契約の手続きを行います。
契約の段階で子どもへの支援内容の説明を受けるのでしっかりと把握しておきましょう。
すべての契約手続きが完了すれば、放課後等デイサービスの利用がスタートとなります。
放課後等デイサービスは、お子さまと保護者の方のサポーター
放課後等デイサービスは、お子さまに対する発達支援(療育)だけではなく、お子さまを支える保護者の方に対するサポートもおこなっています。
施設のスタッフに育児や教育に関する相談をしたり、通所する保護者の方同士のコミュニケーションをとったりすることで、「困りごとや悩みごとを誰かに話せる」という安心感を得ることもできます。
また、通所型のサービスのため、お子さまが施設に通っている間に、保護者の方の時間を確保することもできます。
まとめ
- 放課後等デイサービスは、学校に就学している障害や発達に課題を抱えている子どもを対象とした通所型の福祉サービスです。
- 放課後等デイサービスを利用できる対象年齢は、小学校・中学校・高等学校に通っている子どもで、療育手帳・障がい手帳などを所持していることが原則として決められています。
- 一人ひとりに合わせた支援計画を立て、日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けた支援をおこないます。
- 主な目的は、障害のある子どもが、自身で出来る事を増やしたり、学校や家庭以外の場所での経験を積み、健やかな成長を促しながら、将来的な社会的自立を目指していく場所です。
「メモな備忘録」は、私が役に立った事を忘れないように「メモ」しています。
この記事が、お役に立てれば幸せです。お読みいただき有り難うございます。